午前中の学習発表会が終わり、昼食の時間になりました。学習発表会の日の昼食は毎年恒例で、PTAのお父さん方手作りの豚汁が振る舞われます。この豚汁は、学習発表会当日の朝、PTAのお母さん方の力を借りながら、家庭教育学級で男の料理教室を実施して作ってくださったものです。また、各家庭からおにぎりも持ってきてくださっていて、温かくて愛情こもった昼食をいただきました。豚汁は具がたくさん入っていて、みそで味付けをしているけれどクリーミーな味がして、とてもおいしかったです。

【湯気がもくもく、食欲をそそります】
そして、午後からはわくわく学習発表会が始まりました。これは総合的な学習の時間(わくわく学習:ウッジョブ諸塚)で学習したことを1・2年生は「しいたけで元気」という劇、3~4年生はポスターセッションでの発表をしました。
1・2年生はしいたけに関するクイズを会場の方々に出題し、しいたけの栽培方法を分かりやすく説明してくれました。時折イノシシやシカが出てきて、しいたけに関する知識を教えてくれるという演出もあり、楽しく学ぶことができました。毎日のように観察・お世話をしている1・2年生だからこそ発表できる内容でした。
その後3~6年生のポスターセッションが行われました。1人10分(発表7分、質疑応答3分)で、これまで学習してきたことを4つのブースに分かれて発表しました。3年生はプロセッサーについて、4年生は苗木袋(きけんおまもリュック)について、5年生は木の製品開発班、絵本作り班、6年生はポスター作成班、リーフレット作成班とそれぞれの学習内容を発表しました。これまで、どのようにしたら自分たちの学習した成果を聞いている人に分かりやすく、興味をもって聞いてもらえるかを考え、何度も何度も練習を積み重ねてきました。その練習が子どもたちの自信となり、本番ではどの子どもたちも立派に発表していました。

【3年生:プロセッサーを段ボールで作り、その過程で学んだことを発表しました】

【4年生:きけんおまもリュックを作る過程で出てきた心情の変化がありました】

【5年生:製品開発班 工作にならないために・・・この課題に向き合いました】

【6年生:リーフレット作成班:どうしたら魅力を伝えられるリーフレットができるか考えました】
それぞれ、学習を進める中で色々なハテナが出てきて、それを1つひとつ解決していきました。わくわく学習応援隊の方々や業者の方々の力も借りながら、自分たちの力でできるところは時間をかけて作成していきました。そのため、誰もが自分の発表には気持ちを込めることができ、その子どもにしかできないプレゼンテーションができたと思います。
発表の後の質疑応答の時間では、「シーソーに神楽を彫った版木を使った理由は何ですか」とか「木の絵本の次は木で何を作ってみたいですか?」などの質問が出され、「戸下神楽をPRしたいし、有名にしたいからです。」とか「おもちゃを入れる箱を木で作ってみたい」等と答えていました。予想していなかった質問を受け、答えに窮する場面も見られましたが、きちんと受け止め、自分の意見を発表していました。
その後、パネルディスカッションが行われました。この時間は、わくわく学習応援隊の方々や5~6年生、5・6年の担任の先生が「わくわく学習を通して学んだこと」を語り合い、大学の先生方にコメンテーターとして参加していただきまました。


【林業のプロフェッショナルの方々の貴重なご意見をいただきました】
その話合いの中で、林業の過程を学習していくことの大切さや人と人とのつながり、自分1人では作れないものに挑戦すること等のヒントをいただきました。この1年で林業について学習してきた子どもたちも、次年度学年が変わり新たなステージにたつと見え方も考え方も違ってきます。次年度以降も、子どもたちががむしゃらにわくわく学習に取り組めていけたらいいなと思います。
9月のわくわく学習応援隊の発足式以前も様々な形でウッジョブ諸塚にご協力いただいていましたが、2学期以降更に様々な方にウッジョブ諸塚をご支援いただきました。おかげ様で、子どもたちも職員もとてもいい学びを得ることができました。子どもたちにとって、身近にあったけれど内容をよく知らなかった林業が、今回の学習を通して林業に携わる方々の思いに触れたり、実際に体験をしたりすることで、今では本当に身近なものになったと思います。そして、林業の大切さ、木の大切さ、人と人とのつながりを実感していることと思います。今年度のウッジョブ諸塚を支えてくださり、本当にありがとうございました。
次年度もどうぞウッジョブ諸塚をよろしくお願いいたします。
 諸塚村立荒谷小学校
諸塚村立荒谷小学校




 諸塚村立荒谷小学校
諸塚村立荒谷小学校

















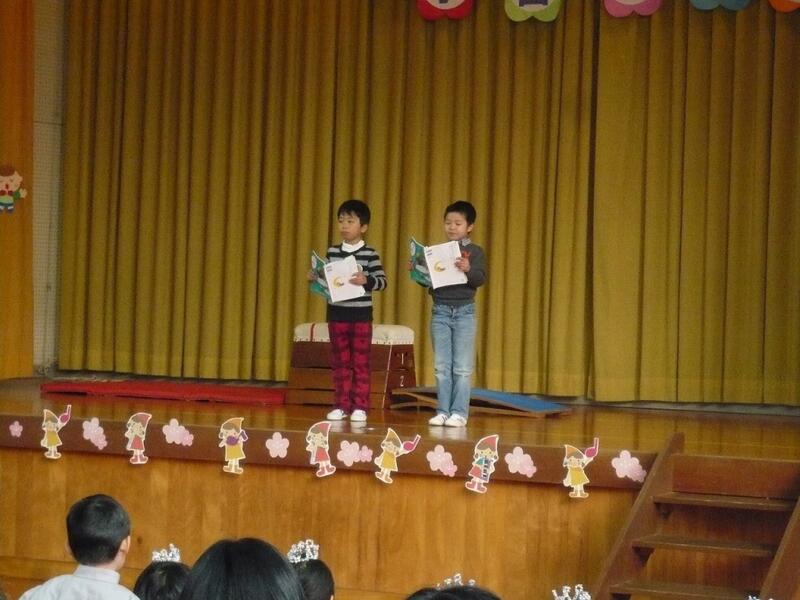
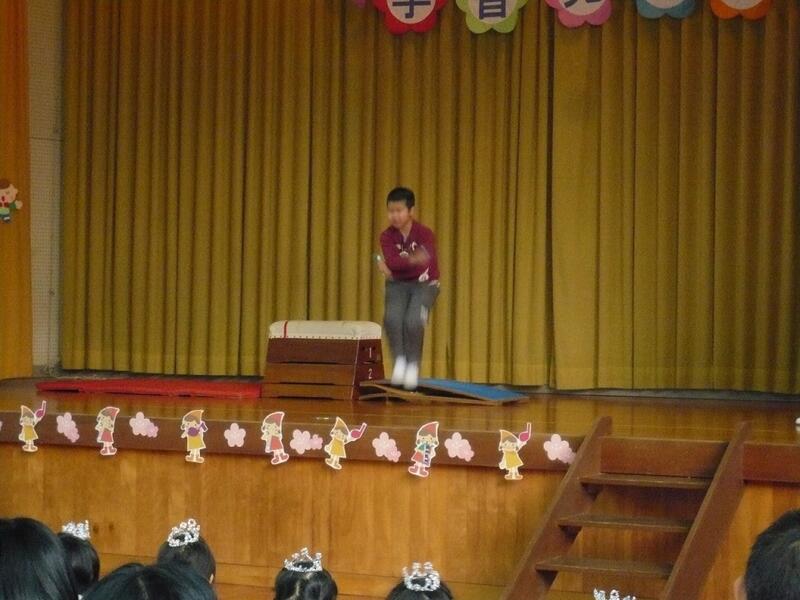
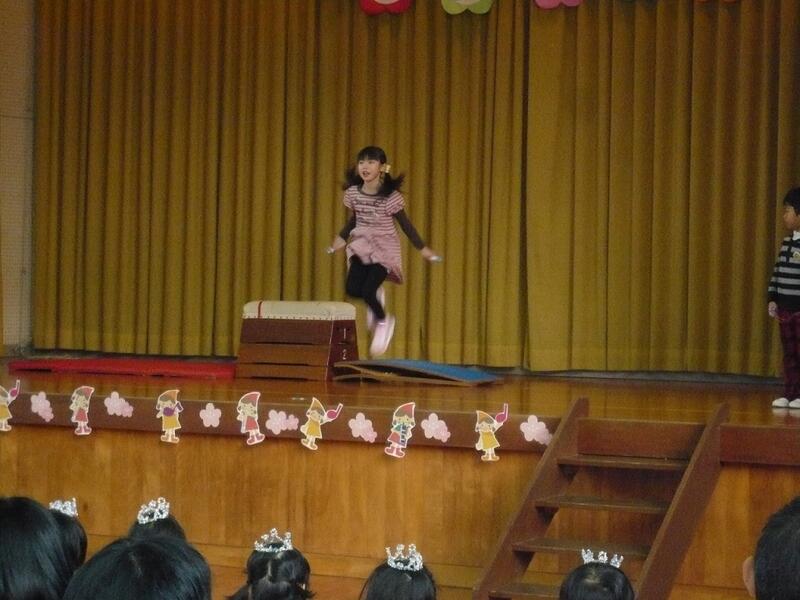














 〒883-1301
〒883-1301