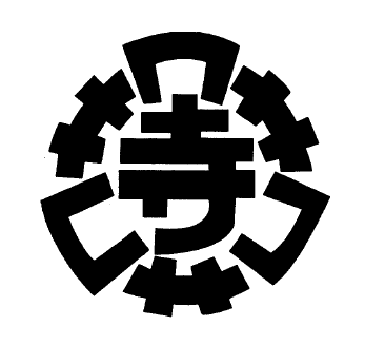
ホームページへ
ようこそ!

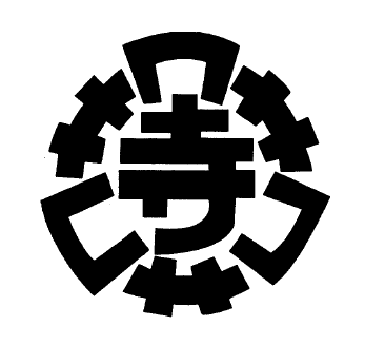
ホームページへ
ようこそ!
GIGAスクール構想のGIGA(ギガ)は、ある英単語の頭文字です。
Global and Innvation Gateway for All
(全ての児童・生徒のための世界につながる革新的な扉)
本校でも、児童1人1端末、タブレットPCが配られています。
タブレットを使うと、今までの学習とは全く違う学習ができます。
例えば、ハードル走の学習。
ハードルを跳び越すたびに、頭の位置が上下しないようにすることが大切です。
ただし、自分で意識していても上下してしまうものです。
友達から
「今の良かったよ」
と言われても、何が良かったのか、どんなフォームだったのかを振り返る方法がありませんでした。
ところが、この写真のように、友達にタブレットで動画を撮影してもらうと、自分で後から確認できます。
そのおかげで、自分の跳び越す感覚と実際の動きを近づけることができます。
例えば、調べ学習。
5年生国語科で、タブレットを効果的に使っていました。
タブレットの良さは、インターネットに接続していることで、疑問に思ったことをすぐに調べられることです。
こんな活用の仕方が、普段から身についてくるといいですね。
子ども達が大きくなった未来には、おそらく今以上にICTが発展します。
メタバース、DeFi(ディファイ)、ブロックチェーン、NFT、DAO・・・
様々なチャンスがつかめるよう、正しい知識と技術、そして適切な表現・発信ができるようになってもらいたいですね。
そして、世界とどんどんつながる子ども達へと育っていってもらいたいです。
1年生は、小学校に入学して初めてのプール。
梅雨の時期ですので、気温や水温が上がりにくいのですが、この日は気温+水温=50℃を超えました。
曇っていても、絶好のプール日和。
準備運動に余念がありません。
さすが、1年生。
先生と同じように、準備運動できました。
シャワーの洗礼を受けます。
しっかり体を洗ったら・・・
さあ、プールへ。
いささか、緊張しているようです。
それでも、中に入って活動していくと、楽しそうにしていました。
水に顔をつけるのも、みんなと一緒でへっちゃらです。
水に親しむ子どもたち。
1年生の楽しい歓声が、プールから地域へ響いていました。
そこには、凛とした緊張感が漂っていました。
夏の暑さもありましたが、白熱する子どもたちの真剣なやりとりに、体育館がさらにヒートアップしているようでした。
6月16日(木)
校内牧水かるた大会
今年度、初めて行うことができました。
もちろんコロナ対策を万全にし、静かな、熱き戦いを子どもたちが繰り広げました。
牧水短歌の朗詠が、体育館に響き渡っていました。
これぞ、寺迫の子ども達。
夏の日向市牧水かるた大会へ向けて、さらに技に磨きをかけます。
登山のあと、お風呂で汗を流したら・・・
お待ちかねの夕食です。
ビュッフェ形式ですので、自分なりに量を考えて盛り付けています。
大人になるためにも、大切な体験ですね。
夕食後は、キャンドルの集い。
キャンドルに灯された火を見つめ、今日一日を振り返りました。
あたたかな炎のおかげで、神聖でほっとするような気持ちになったことでしょう。
美々津小学校の皆さんと、お互いに学校紹介の出し物
そして、署員の皆様の用意してくださったレクリエーションのおかげで、
とても楽しいひと時を過ごせました。
その後は、ぐっすり就寝できました。
<翌日の話は、また別の機会に>
6月9日(木)・10日(金)
寺迫小学校と、お隣の美々津小学校の5年生とで、宿泊学習が行われました。
向かうは、むかばき少年自然の家。
初日のメインイベントは登山。
むかばき山へ登っていきます。
アドベンチャー感、満載の道です。

でも、ご褒美になるのは・・・昼食です。
空腹と自然の空気が、最高の調味料となったことでしょう。
そして、山登り最高のご褒美と言えば・・・山頂からの景色です。
あいにく、山頂が雲の中に入っており、遠くまでは見えませんでした。
しかし、子どもたちは山頂へ向かって流れる雲を触ったり、食べたりと、夢のようなことをしていました。
そして、恒例のヤッホーコール。
麓の、自然の家とお互いにヤッホーの声を掛け合うというものです。
まさか、そんな遠くから声が届くと思っていない子どもたち。
所員の方の声が聞こえると、驚きの喚声が上がっていました。
<次回へ続く>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |