 諸塚村立荒谷小学校
諸塚村立荒谷小学校




 諸塚村立荒谷小学校
諸塚村立荒谷小学校



1月25日は、献立を作ってくださる諸塚中学校の栄養教諭の先生、献立をもとに諸塚の野菜を学校まで届けてくださる地域の方(本校児童のおばあちゃん)、おいしい給食を毎日作ってくださる調理員の先生をお招きして、給食感謝集会をしました。
3人の方々がおいしい給食のために毎日どのようなことをされているのかを知り、改めて感謝の気持ちを持つことができました。




【事前に給食室を見学に行きました。大きなお鍋や冷蔵庫に驚いていました。】
栄養教諭の先生からは、合同学活で「食事のマナー」について教えていただきました。これまでの自分自身を振り返りながら、みんなでおいしく楽しく気持ちよく食べるための正しいマナーについて学ぶことができました。



【はじめて栄養教諭の先生と給食を食べ、子どもたちもとてもうれしそうに話していました。ドッグパンの上手な食べ方の秘訣を教えていただきました。】
大工をされている地域の方が、二重跳びの感覚をつかむのにとても効果的な練習用板を作ってくださいました。早速、業間の時間にお披露目をし、子どもたちはバネのようによく跳ねる板の上で楽しそうに何度もチャレンジしていました。子どもたちのためにといつもご尽力くださる地域の方に感謝しつつ、寒さに負けない体づくりにたくさん活用していきたいと思います。



1月22日(火)は新入生体験入学の日。かわいらしい荒川保育所の年長さんが大きなランドセルを背負って、少し緊張した様子で登校してきました。案内係の3・4年生が校内の場所や役割をひとつひとつ優しく案内していました。
年長さんが学校に来たことがうれしくてたまらない子どもたち。張り切って学校のことを教えたり、話しかけたりしていました。





【給食や掃除、授業の体験も頑張っていました。】
体育では「プレルボール」をしています。1チーム4人の2チームがネットをはさみ、自分のコート内でバウンドして3回目のバウンドパスで相手のコートに打ち返すゲームです。勝つためにはどうしたら良いか、チームで話合い、協力しながら体を動かしています。



合同音楽では、学習発表会に向けて体育館での練習が始まりました。今回ははじめて保育所生も一緒に合同合奏の練習をしました。少しずつですが、リズムが合うようになってきてうれしそうな子どもたち。学習発表会までいよいよあと約20日となりました。わくわく学習の発表や学級ごとの学習発表などの練習も毎日頑張っています。





1月17日(木)は、火災の避難訓練を行い、今年も講師として、諸塚村消防団第4部12名の団員の方々、諸塚村役場の消防担当の方にお越しいただきました。
「操法訓練」と「規律訓練」を見せていただき、迅速で力強い諸塚村消防団第4部団員の方々の姿に子どもたちも驚いていました。避難訓練をとおして、消防団の方々が諸塚村を守るために色々な努力をしてくださっていること、火災から命を守るためにはどうしたら良いかを考えて行動することの大切さを学びました。



【放水体験をさせていただきました。ホースがとても重かったようです。】
本年度も『荒谷小学校荒川保育所学習発表会』を行います。
日程、プログラムは下記のとおりです。
たくさんのご参加をお待ちしております。
期日:平成31年2月10日(日)
時間:8時50分~12時00分
平成30年度学習発表会プログラム.JPG
【平成29年度学習発表会の様子です】
1月8日(火)は3学期始業の日でした。久しぶりの再会に子どもたちもとてもうれしそうでした。
始業式では、3年生が児童代表の言葉で、「続けることでできなかったことができるようになる練習が好きだから、3学期は『剣道』、『学習発表会』、そして、『大好きな6年生を送り出す卒業式』の3つの『練習』をコツコツとがんばりたい。」と立派に発表しました。
6年生は、「最後の学期なので、自分の姿や言葉で、下学年にリーダーについて伝えたり教えたりしていきたい」と頼もしい目標を発表しました。

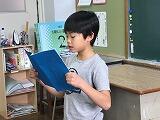

子ども一人一人がしっかりと目標を持って、新学期を迎えることができました。3学期は他の学期に比べると日数は短くなりますが、1年間のまとめの学期にもなります。4月よりも大きく成長した子どもたちと30年度の「修了の日」が迎えられるよう、1日1日を大切にしていきたいと思います。
【誕生日が近かった地域の方が遊びに来てくださったので、みんなでお祝いをしました。子どもたちもとてもうれしそうでした。】
12月21日(金)は2学期終業の日でした。終業式では、児童代表の5年生が2学期を振り返り、「協力」と「感謝」を感じ学ぶことができたと立派に発表しました。合同学活では、冬休みに向けて学習、生活、健康安全について気をつけることを確認しました。


2学期、たくさんの行事がある中で、地域の方々に支えられながら子ども一人一人が何事にも果敢に挑戦し、全力で楽しんで、成長することができたこと、13人全員がほとんど欠席することなく毎日元気に過ごし、2学期終業の日を迎えられたことをとてもうれしく思います。
今月から2月の学習発表会に向けて、合同合奏の練習が始まりました。13人でリズムを合わせて一曲を完成させるために、各自真剣な表情で練習をしています。「リズムが合うように、冬休みや3学期も練習を頑張りたい」と意欲満々な子どもたちです。






文化芸術による子供の育成事業(芸術家派遣事業)として、「んまつーポス」の方々に3日間お越しいただき、表現運動や創作ダンスをしました。常にわくわくした表情で楽しそうにダンスを創作していく子どもたち。表現することの楽しさを全身で感じた3日間となりました。








3・4年生が中心になってお楽しみ会をしました。子どもたち、職員みんなでサッカーやドッジボールをして楽しみました。朝は分厚い上着を着てきますが、まだまだ半袖で元気な子どもたち。今日もたくましく運動場を走り回っていました。




今週の掃除の時間は、普段とは違う体育館や窓、教室の隅々などを掃除する「学期末清掃」週間です。新しい年を気持ちよく迎えられるよう、一人一人が一生懸命頑張って学校をきれいにしています。







今月は5・6年生の表現集会でした。お互いのすごいところを英語でスラスラと紹介し合ったり、合奏や合唱でハーモニーを奏でたり、さすが高学年といったすばらしい発表でした。1~4年生からも「すごい」、「5・6年生のようにできるようになりたい」という感想が多くあがりました。





12月7日は、長距離走大会・もちつき大会を行いました。
長距離走大会では、これまでの練習の成果に加えて、たくさんの保護者の方々の声援にパワーをもらい、全員が自己ベストの記録でゴールすることができました。




午後は、もちつき大会です。力いっぱいもちをつき、悪戦苦闘しながらも小さな手で丸めていました。つきたてのおもちはおいしかったようで、うれしそうに頬張っていました。






おいしいもち米を提供してくださった地域の方、5日(水)から準備をしてくださり、当日も朝から夕方までずっと動きっぱなしで協力、応援してくださった保護者の方々に感謝の気持ちでいっぱいです。子どもたちも充実した楽しい1日を過ごすことができました。


毎月16日前後は、諸塚の食材を多く使った給食「諸塚学校給食の日」を実施しています。今月の諸塚学校給食の日は、特別に生産者の方や実行委員の方をお招きしてのふれあい給食でした。全員で6人の方々にお越しいただき、子どもたちは笑顔いっぱい、終始うれしそうに交流を深めていました。また、滅多に聞くことのできない、諸塚の食材のことを直接聞くことができ、有意義な時間となりました。








今回の表現集会は中学年でした。リコーダーを演奏したり、駄賃づけ唄を披露したりした後は、「じゅうごやさんのもちつき」の手遊びうたをみんなと一緒にしました。真剣な姿を見せてくれたり、笑顔で楽しむ姿を見せてくれたりと、メリハリのある3・4年生らしい楽しい表現集会でした。



11月20日(火)は読書集会をしました。本の一部を読み聞かせで紹介してくれたり、「ぐりとぐら」の絵本を、劇を交えながら紹介してくれたりしました。すぐにでも本が読みたくなるような楽しい集会でした。

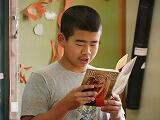














地域の方の田んぼをお借りして田植えをしてから約5ヶ月。立派に成長した稲穂で田んぼ全体が黄金色となり、今年も大豊作でした。
実際に稲を刈ったり、機械を使っての稲刈りも一人ずつ体験させていただいたりしました。地域の方が最後におっしゃっていた「作物の一番の大好物は『人の足音』、どれだけ足を運んでお世話をしたかで成長は変わる」という言葉はとても感慨深いものでした。







【子どもたちのためにと毎年ご協力してくださる地域の方々に感謝です。12月のもちつき大会では、いただいたお米を大切においしくいただきたいと思います。】
〇 上記に閉校関係の項目を追加しております。本校関係者の皆様は是非閲覧していただき、添付ファイルのURLもしくはQRコードから閉校に係わる回答をしていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
〇 「空き瓶(一升瓶・ビール瓶のみ)回収」期間を2月28日(土)まで延長します。子どもたちの活動費のため、ご協力をお願いいたします。
〇 令和8年度の主な行事を入力しました。★閉校式は令和9年2月13日(土)実施予定です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 2 | 6 | 7 1 |
8 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 2 | 16 1 | 17 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 2 | 26 | 27 | 28 |
 〒883-1301
〒883-1301