 諸塚村立荒谷小学校
諸塚村立荒谷小学校




 諸塚村立荒谷小学校
諸塚村立荒谷小学校



二日目、土々呂中学校と合同で、朝のつどいをしました。朝のつどいでは、朝のあいさつを6年生が、3年生がラジオ体操を代表で立派に発表しました。

朝ごはんをもりもりと食べた後は、ウォークラリーです。地図を読みながら、クイズを解きながら、班ごとに協力してゴールを目指しました。


ずっと一緒に二日間をともに過ごした子どもたち。ルールを守ることの大切さはもちろん、土々呂中学校の生徒やむかばき職員の方々の温かさ、仲間と協力することの大切さ、自然の豊かさなどたくさんのことを学んだ二日間となりました。
6月21日(木)、全校宿泊学習で延岡市のむかばき青少年自然の家に1泊2日で行きました。
二日間の様子を少しずつですが、紹介します。
まずはじめは、滝トレッキングです。前日までの雨の影響で途中までの登山となりましたが、ヘビや見たことのない蜘蛛を発見するなど、貴重な体験をすることができました。
マスのつかみ取りにもチャレンジしました。ぬるぬるするマスを捕まえるのにみんな苦労していました。

捕まえたマスで調理にもチャレンジしました。「命をいただくこと」を体験して学びながら、自分で調理したマスのおいしさに感激していました。


お風呂や夕食を済ませた後は、天体観測です。曇り空でしたが、木星や月の明るさに子どもたちも驚いていました。


天体観測の後は、土々呂中学校やむかばきの職員の方々へダンスの発表をしてエールを贈りました。たくさんの拍手をおくられ、とてもうれしかったようでした。
朝から眠るまですべての活動に全力で取り組み楽しんだ子どもたち。夜はぐっすりと眠っていました。
6月12日、梅雨とは思えない青空の下で田植えとプール開きを行いました。
田植えでは、芋の畑と同様、地域の方の田んぼをお借りして体験をさせていただきました。列に沿って真っ直ぐに植えるのに苦労しながらも、1本1本丁寧に植えることができました。泥の中に手足を入れる感触もとても楽しかったようでした。


田植えで泥まみれになった後は、こちらも心待ちにしていたプール開きです。「50m泳ぐ」、「平泳ぎができるようになる」などそれぞれが今年の目標を発表しました。これから約1ヶ月行われる水泳学習、子どもたちが目標に向かってどのように成長していくのか見守っていきたいと思います。


6月8日、いつもおいしい給食を作ってくださる調理員の先生のお誕生日が近かったので、給食の時間にお祝いをして、一緒に給食を食べました。調理員の先生と一緒に給食を食べることがとてもうれしかった子どもたち。楽しい話をしながら、いつも以上にもりもりおいしそうに給食を食べていました。


今年も地域の方の畑をお借りし、芋の苗植えをしました。粘り気の強い土に悪戦苦闘しながらも苗が抜けないように土をかぶせることができました。畑を貸してくださり、この日のために畑を耕したりマルチを貼ったり等の準備をしてくださった地域の方への感謝の気持ちを忘れず、苗がどのように成長しておいしいサツマイモができるのか、わくわく学習等で観察しながら見守っていきたいと思います。



【11月の収穫が今からとても待ち遠しいようです。】

【地域の方、毎年お世話をしてくださりありがとうございます。】




5月28日(月)は森林体験学習で植林体験と作業現場の見学や体験をしました。役場の方、耳川広域森林組合諸塚支所の方々、東臼杵郡農林振興局諸塚駐在所の方々、吉永林業の方々とたくさんの方々が講師として林業のことを教えてくださいました。

【5月22日は、事前学習をしました。】
スギの苗を真っ直ぐに植えることの大変さ、雨の日に林業をすることの大変さ、命を守るための服装の準備の大変さなどを体験しながら学び、そして、何よりその大変なことを確実に、迅速に行っている林業の方々のすごさを実感した学習となりました。


【たくさんの方々が子どもたちのために駆けつけてくださいました。ありがとうございました。】





5月25日(金)の参観授業で全校での歯みがき教室を行いました。太田歯科医院の歯科衛生士さんに来ていただき、正しい歯のみがき方や習慣づけることの大切さを体験しながら学びました。



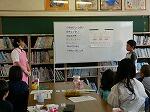


6校時は、心肺蘇生法講習会でした。日本赤十字社宮崎県支部の方に講師として来ていただき、保護者、職員と一緒に5・6年生も参加して、心肺蘇生法やAEDの使い方を教えていただきました。


5月11日(金)は、春の遠足で、せせらぎの里(特別養護老人ホーム)と池の窪グリーンパークに行きました。
せせらぎの里では、はじめにダンスと将来の夢の発表をして、せせらぎの里の方々へエールを送りました。笑顔いっぱいの発表で利用者の方々へ元気を届けることができました。エールを送った後は、グループに分かれてすごろくゲームでのふれあいです。はじめは緊張していましたが、事前に職員の方々に教えていただいた接し方でハイタッチをしたり、一緒に歌を歌ったりしながら自然と笑顔が増えていき、楽しくふれあうことができました。その他にも、聴診器やリフトバスの乗車や操作など貴重な体験をたくさんさせていただき、色々な職業があることを学びました。





せせらぎの里訪問の後は、池の窪グリーンパークに行きました。早速、お弁当の時間です。今回もそれぞれ目標を立てお弁当作りにチャレンジしました。とてもおいしそうに、うれしそうに自分で作ったお弁当を食べていました。

お弁当を食べた後は、遊具や草スキーをして遊びました。


今年度初めての13人での遠足。たくさんの貴重な体験を通して、思い出に残る楽しい1日にすることができました。
明日はいよいよ春の遠足です。弁当の日やせせらぎの里訪問に向けての事前学習を通して、子ども一人一人が目標や見通しを持つことができました。今年度初めての遠足、子どもたちも楽しみで仕方がないようです。
弁当の日の事前学習の様子です。1日分、1食分の栄養について学びました。


せせらぎの里訪問に向けて、すごろく作りや発表の準備をしている様子です。


5月7日(月)は、寿会の方々との交流をしました。雨のため、室内でのグランドゴルフとなりましたが、今年度も19名とたくさんの方々が参加してくださり、大盛り上がりの大会となりました。


グランドゴルフで体を動かした後は、給食を食べながら交流を深めました。寿会の方々と昔の話や好きなことなどの話をして、とても楽しかったようでした。





5月11日(金)は春の遠足でせせらぎの里(特別養護老人ホーム)を訪問し、利用者の方々と交流をする予定となっています。5月2日(火)は、訪問の事前学習として職員の方々から認知症や高齢者の方々のことについて教えていただきました。
認知症や高齢者の方々のこと、接し方を分かりやすく教えていただき、訪問に向けて、それぞれ目標を立てたり、意欲が高めたりすることができました。




4月24日(火)、今年度初めての参観日を行いました。
1・2年生は、体育でお母さんやお父さんたちと一緒に体を動かしました。





【お母さんやお父さんたちと一緒に体育ができて、いつも以上に元気いっぱいの1・2年生でした。】
3・4年生は、図工でストローや筆を使って、自由に絵を描きました。



【みんな真剣な表情で黙々と絵を描いていました。】
5・6年生は、算数の学習をしました。
【複式授業でどんどん学んでいく5・6年生。さすがです。】
参観授業の後は、合同懇談会、PTA総会を行いました。

お忙しい中、大勢の方にご出会していただき、ありがとうございました。PTA総会で協議が進められ今年度の各部の活動計画の見通しももつことができました。地域・保護者の皆様・学校が今まで以上につながり、有意義なPTA活動が進められるよう、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。








今年度も家庭教育学級の方々が朝の時間に絵本の読み聞かせに来てくださることになりました。4月18日は今年度初の読み聞かせで、2年生の保護者の方が来てくださいました。みんなとても楽しそうに聞き入っていました。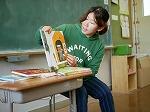










【体育館中に元気な声が響いていました。】



【1・2年生は20秒間のブリッジにチャレンジ!】
入学式の次の日、全校児童13人での学校生活がスタートしました。1年生が入学してくることをずっと心待ちにしていた2~6年生。朝から張り切って優しく色々なことを教えてあげていました。1年生は、昨年度から約2㎞の距離を登校班のメンバーで歩く練習をしていたので、大きなランドセルを背負いながらも初日から元気に登校することができました。
朝の活動の時間は登下校指導をしました。
【早速、意欲的に発表する1年生。とても頼もしいです。】
13人での初めての給食の時間です。この日のメニューは、「ミニミルクパン、スパゲッティミートソース、青豆サラダ、お祝いいちごゼリー」。新しくほたきゅう委員会に入った新3年生。前の日から読む練習をがんばって、献立の一口メモを大きな声で読むことができました。
1年生2人が増えて、とても賑やかな給食の時間となりました。今年の給食もとてもおいしく、うれしそうに完食した子どもたちでした。


4月10日は、みんながとても楽しみにしていた1年生2名が入学してくる日。色とりどりのきれいな花が花壇や植木鉢にたくさん咲いて、1年生の入学を歓迎しているようでした。

入学式、はじめに花のアーチをくぐって入場です。










笑顔いっぱい、元気いっぱい、花いっぱいのとても素敵な入学式となりました。ようやく全校児童13名が揃い、子どもたちもとってもうれしそうです。保護者の皆様、地域の皆様、今年度も荒谷小の子どもたちのために、ご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
4月6日(金)は平成30年度始業の日でした。曇り空の朝でしたが、久しぶりに校門から「おはようございます!よろしくお願いします!」という子どもたちの元気な声が校庭に響きました。
はじめに新任式を行いました。今年は、校長先生、担任の先生、荒川保育所へ保育士の先生が赴任されました。
【みんなで花のアーチを作ってお出迎えです。】


【お一人ずつご挨拶がありました。】
新5年生が歓迎の言葉を述べました。荒谷小学校の魅力や、今年度の抱負を分かりやすく伝えていました。
新任式の後は、1学期の始業式を行いました。
校長先生のお話では、目に見えないことでも見えることでも何かひとつ「これだけは一番になりたい!」と思える目標を決めることを約束しました。
【子どもたちも目を輝かせて話を聴いていました。】
新6年生が児童代表の言葉で今年度の抱負を2つ発表しました。「一つ目は、昨年度の6年生のように目を配ることや諦めないことを大切に、まとめる力や挑戦する力を身に付けたい。二つ目は小学校生活最後の年として、友だちや家族、先生、地域の人たちへの感謝の気持ちを大切に、恩返しをしていきたい。」荒谷小学校の新しいリーダーらしい、とても頼もしい発表でした。
次に2~5年生が新年度の目標を発表しました。
【2年生】左の児童から順番に目標をご紹介します。
◯人を大切にしたい。
◯新しい1年生の手本になるようにがんばりたい。
◯自分に負けないようにがんばりたい。
◯何事も諦めない。
【3年生】
◯あいさつと立腰をがんばりたい。
◯聴くことを心がけたい。
◯集中すること、「間違いは宝だ」を大切に挑戦したい。
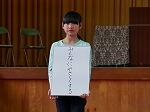
【4年生】
◯みんなに優しくしたい。
◯外で運動していきたい。
【5年生】
◯みんなで協力して何事もがんばりたい、病気にならないように健康に気をつけたい。
やる気みなぎる目標発表の後は、今年度初の校歌斉唱です。
【4年生女子二人が、息ぴったりで指揮と伴奏をしました。】
子どもたちの今日の楽しみの一つでもあった「担任発表」の瞬間です。



【みんなとってもうれしそうでした。】
いよいよ30年度がスタートしました。3月には6年生が卒業し、お二人の先生が転出され、とても寂しい別れがありましたが、新年度、子どもたちは新たな目標をしっかりと持ち、新しい学びに胸を膨らませ、やる気に満ちているようです。10日の入学式で1年生が入ってくること、13人が揃うこともとても楽しみにしているようでした。保護者・地域の皆様、関係者の皆様、平成30年度もどうぞ荒谷小学校をよろしくお願いします。
【地域の皆様あっての荒谷小学校です。今年度もどうぞよろしくお願いします。】

〇 上記に閉校関係の項目を追加しております。本校関係者の皆様は是非閲覧していただき、添付ファイルのURLもしくはQRコードから閉校に係わる回答をしていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
〇 「空き瓶(一升瓶・ビール瓶のみ)回収」期間を2月28日(土)まで延長します。子どもたちの活動費のため、ご協力をお願いいたします。
〇 令和8年度の主な行事を入力しました。★閉校式は令和9年2月13日(土)実施予定です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 2 | 6 | 7 1 |
8 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 2 | 16 1 | 17 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 2 | 26 | 27 | 28 |
 〒883-1301
〒883-1301