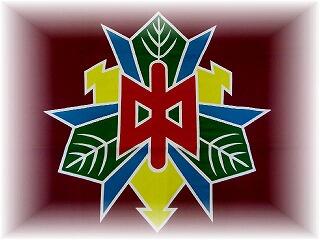2016年10月の記事一覧
凡事徹底
もうすぐ10月も終わり、来週からは県大会が行われますが、出場権を逃した榎原中も立ち止まっている暇はなく、最後の夏に向けて計画的にチーム力を強化しているところです。そこで地区大会終了後もたくさんの練習試合に参加させていただいています。
10月1日・・・吾田中体育館(2勝2敗:吾田中)
10月8日・・・平岩小中体育館(7勝1敗:門川中に3勝1敗、延岡南中に4勝)
10月9日・・・榎原地区体育館(2勝2敗:吾田中)
10月10日・・・佐土原中体育館(4勝6敗:宮崎西中・佐土原中・福島中に2敗、姫城中と緒方中に2勝)
10月16日・・・高城総合体育館(8勝1敗:宇都中に1勝1敗、門川中に2勝、都農中に2勝、高原中に3勝)
10月22日・・・山田地区体育館(7勝2敗:妻ヶ丘中に3勝1敗、三股中に4勝1敗)
10月29日・・・八代中・宮崎西中体育館(5勝6敗:吾田中に3敗、姫城中に1敗、門川中に1勝2敗、大塚中に2勝、八代中に2勝)
このように、10月は様々な方々の協力やご厚意のおかげで、数多くの練習試合を経験させていただくことができました。このうち私が指導することができたのは高城総合体育館での練習試合のみでしたが、やはり平日の練習でやっていることが練習ゲームの中で生かされてない、生かそうとしていない場面が多々ありました。
今榎原中は、冬のJA共催杯や夏の中総体に向けて、様々なフォーメーションやポジションを試しているところです。そのような状況ですから、当然ゲーム展開は安定しないのですが、新しいことに取り組む上で大切なことは、失敗を恐れずチャレンジするということと、今までやってきたことをきちんとやるということです。
タイトルの“凡事徹底”とは、“なんでもないような当たり前のことを徹底的に行うこと、または、当たり前のことを極めて他人の追随を許さないこと“などを意味する四字熟語です。榎原中はこの当たり前のことを当たり前にやるということが、ある程度できているのですが徹底できていません。
これまでの練習でずっとやってきたことには、あいさつ、返事、声かけ、服装、レシーブの面作り、ブロックのステップ、スパイクのフォーム、サーブのねらい、表情を作ることなどがあります。これらのことは意識次第でできることですが、徹底することができていません。当然、できることをやらないのに、できないことができるようになるはずがありません。
何かにチャレンジするためには、その状況をできる限り数多く作らなければなりません。しかし、練習試合の状況を確認してみると、チャレンジせずにエースやサーブのみで勝利するというような結果オーライで終わっていたり、お見合いやサーブミス、スパイクミスなどの自分たちの単純なミスを繰り返すなど、チャレンジする以前の段階でつまづいていたりと、ほとんどチャレンジすることができていません。
私がいるといろんなことについてつい言い過ぎてしまい、そのときはすることができるのですが、本当の力にはなっていません。そういう意味では、私が県選抜でチームにつけない今はチームが成長する絶好のチャンスなのですが、ほとんど自分たちで考えることができないのが現状です。本当の力を身につけるためには、自分たちの課題や良かったところを共有して、次にどうつなげていくか考えて、それを実行しなければなりません。
もうすぐチーム作りは“破”の時期に入ります。次のステップに進むためにも、しっかりと目的や目標を見据えて、まずは信頼関係を強固にするための五箇条をしっかりと意識していきましょう。