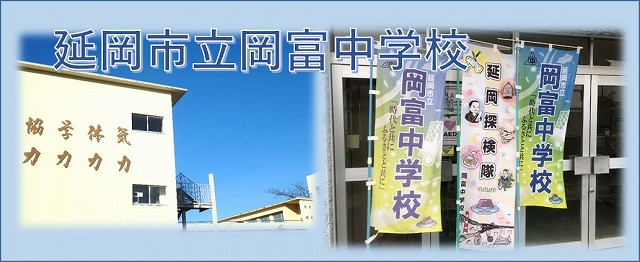人権・同和教育
2020年6月の記事一覧
延岡大空襲の日
6月29日は、延岡大空襲の慰霊の日です。
当時の岡富中の場所には、県立延岡高等女学校がおかれていました。その女学校も、空襲で焼け落ちてしまいました。ですから、75年前の今朝は、岡富中のあたりは焼け野原だったわけです。その名残が、からみレンガの塀になります。
1945年6月29日、午前1時46分ごろから始まった空襲は、宮崎県内で最も規模が大きいものでした。飛来したB29などの航空機は117機。投下された焼夷弾は10万発。東京大空襲における飛来した航空機は520機あまりということですから、その5分の1と考えていいでしょう。
かつて、防空法という法律がありました。その第8条に、消火における退去の禁止と応急消火義務という項目があります。最初は条件付きの規定でしたが、太平洋戦争とともにそれらが強化され、空襲時、国民は全面的に退去することができなくなってしまいました。つまり、空襲だからといって、我先に避難することはできませんでした。「逃げ遅れた」のではなく、「逃がしてくれなかった」(それも国が)のです。
「なぜ、人権教育で平和教育をするのですか」よく聞かれます。戦時は自らの生命すら自分で保持することは困難で、人権が制限されていました。考える「いとま」すらなかったのです。だから「戦争は最大の人権侵害」といわれます。平和の状態ができて、初めて人権の考えが芽吹きます。「平和なくして人権なし」──それでは、失礼いたします。
当時の岡富中の場所には、県立延岡高等女学校がおかれていました。その女学校も、空襲で焼け落ちてしまいました。ですから、75年前の今朝は、岡富中のあたりは焼け野原だったわけです。その名残が、からみレンガの塀になります。
1945年6月29日、午前1時46分ごろから始まった空襲は、宮崎県内で最も規模が大きいものでした。飛来したB29などの航空機は117機。投下された焼夷弾は10万発。東京大空襲における飛来した航空機は520機あまりということですから、その5分の1と考えていいでしょう。
かつて、防空法という法律がありました。その第8条に、消火における退去の禁止と応急消火義務という項目があります。最初は条件付きの規定でしたが、太平洋戦争とともにそれらが強化され、空襲時、国民は全面的に退去することができなくなってしまいました。つまり、空襲だからといって、我先に避難することはできませんでした。「逃げ遅れた」のではなく、「逃がしてくれなかった」(それも国が)のです。
「なぜ、人権教育で平和教育をするのですか」よく聞かれます。戦時は自らの生命すら自分で保持することは困難で、人権が制限されていました。考える「いとま」すらなかったのです。だから「戦争は最大の人権侵害」といわれます。平和の状態ができて、初めて人権の考えが芽吹きます。「平和なくして人権なし」──それでは、失礼いたします。
危機管理マニュアル
危機管理マニュアル(R7改訂)
{{cabinetFile.CabinetFile.filename}} >
危機管理マニュアル(R7改訂)
| 名前 | 更新日 | |
|---|---|---|
|
003 危機管理マニュアル・R7.pdf.pdf
158
|
11/12 |
|
新着情報
パブリック
訪問者カウンタ
2
1
3
8
4
6
8
校訓
気力 ・ 体力 ・ 学力 ・ 協力
学校評価
いじめ防止基本方針
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 1 | 1 1 | 2 2 | 3 | 4 1 | 5 2 | 6 |
7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 2 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
リンク集
延岡市立岡富中学校
宮崎県延岡市本小路75番地2
【TEL】0982-21-6494
【FAX】0982-21-6495
本Webページの著作権は、延岡市立岡富中学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。