幼稚園併設の施設一体型小中一貫校
創立6年目を迎えました!
創立6年目を迎えました!


























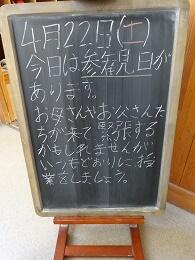






























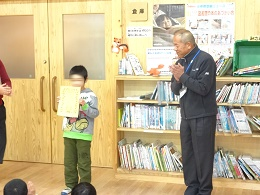
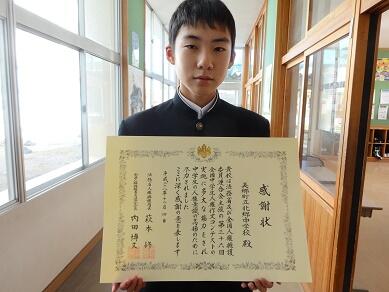
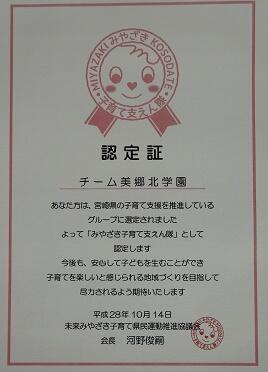













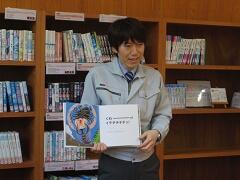






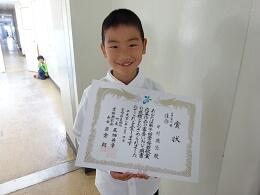











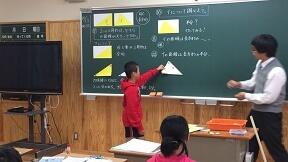






































 |
| ポークカレーライス、海藻サラダ |
 |
| ミニ黒糖パン、ナポリタンスパゲティ、コールスローサラダ |
 |
| 麦ごはん、魚のかわり揚げ、もずく汁 |
 |
| チキンライス、卵とコーンのスープ、フルーツサラダ |
 |
| 麦ごはん、タイピーエン、もやしのナムル |
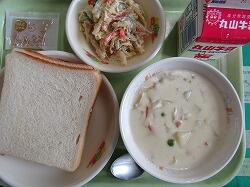 |
| 食パン、クラムチャウダー、マカロニサラダ |
 |
| 麦ごはん、ひじきの五目煮、石狩汁 |
 |
| 親子丼、茎わかめの酢の物 |
 |
| 減量麦ごはん、チキン南蛮、とろろ汁、お祝いケーキ |
 |
| 麦ごはん、豚肉の生姜炒め、スナップえんどうのマリネ、豆腐とあおさのスープ |