今日の給食
2018年1月の記事一覧
2月14日 水曜日
今日はツナサンドです。パンにツナサラダをはさんで食べます。皆さん、ツナサンドを食べるその手はきれいに洗いましたか?手には目に見えない細菌がたくさんいます。せっけんをよく泡立てて、手のひらや手の甲をしっかり洗います。忘れがちな指と指の間、つめ、手首、親指の付け根もよく洗って、水で洗い流します。給食の前には手をきれいに洗うようにしましょう。
・ツナサンド
・かぶのクリーム煮
・牛乳

・ツナサンド
・かぶのクリーム煮
・牛乳

2月13日 火曜日
給食後の片付けはきちんとできていますか?いつもできていたら○、できていなかったら×で答えましょう。
①食べ終わった食器にはごはん粒やおかずの食べ残しがくっつていませんか?
②食器はかごに入れるときに投げていませんか?
③おはしやスプーンの向きはそろえていますか?
きれいに食べ、きれいに片づけること、そして食器や器具を大事に使うことはあたりまえのことです。相手を思いやるにもなりますし、給食を作ってくださったり、片付けてくださったりする調理員の先生方への感謝の気持ちを表すことにもなります。片付け方について振り返ってみましょう。
・中華おこわ
・白菜と肉団子のスープ
・フルーツ杏仁
・牛乳

・中華おこわ
・白菜と肉団子のスープ
・フルーツ杏仁
・牛乳

2月9日 金曜日
おでんに入っているちくわのお話です。ちくわは、魚の肉のすり身を竹などの棒に巻き付けて、焼いたり蒸したりした加工食品です。板の上にすり身をのせた板かまぼこが現れる前は、「ちくわ」がかまぼこと呼ばれ、江戸時代までは高級品でした。板かまぼこと区別するため、串を抜くと筒状になり竹の切り口に似ているので、竹輪かまぼこと呼ぶようになり、略して「竹輪」と呼ばれるようになりました。
・麦ご飯
・一口おでん
・小松菜のごま和え
・牛乳

・麦ご飯
・一口おでん
・小松菜のごま和え
・牛乳

2月8日 木曜日
今日のサラダには、チーズが入っています。みなさんがいつも飲んでいる牛乳は、カルシウムがたくさん含まれていますが、この牛乳をなんとか長い期間保存できないかと考えられたのがチーズなのです。チーズはヨーロッパから来たようなイメージが強いのではないでしょうか?じつは砂漠地帯のアジアが発祥の地なんですよ。羊の胃袋を水筒がわりにして、牛乳をいれて持ち歩いていたところ、暑さによって牛乳がチーズになっていたのが始まりだったそうです。
・ポークカレーライス
・チーズサラダ
・牛乳

・ポークカレーライス
・チーズサラダ
・牛乳

2月7日 水曜日
麦ごはんのお話です。なぜ、麦をごはんに混ぜて食べるようになったのでしょうか?今日は、その秘密に迫ります。昔、戦争をしていた頃、なんとしても勝ってもらおうと、兵士たちにお腹いっぱい白ご飯を食べさせていました。しかし、戦う前に病気で亡くなる人が多く、戦争に負けてしまいました。亡くなった原因は「脚気」という病気にかかっていたからです。脚気は、ビタミンB1が足りなくなる病気です。脚気になると、筋肉の力が弱くなり、心臓がはれるなどして、ひどい時は死んでしまう恐ろしい病気です。この病気からみんなを救ったのは、海軍のお医者さまで、宮崎県生まれの高木兼広さんという方です。脚気になるのは、栄養バランスのかたよりに原因があるとして、兵士たちにビタミンB1の多い麦をご飯に混ぜて食べさせました。するとみるみるうちによくなり、脚気で亡くなる人はいなくなりました。とても大切な働きを持つ麦の入った麦ごはんを残さず食べましょう。
・麦ご飯
・豚肉の生姜炒め
・のっぺい汁
・牛乳

・麦ご飯
・豚肉の生姜炒め
・のっぺい汁
・牛乳

2月6日 火曜日
みなさんは家の手伝いをしていますか?給食当番のつぎ分け方を見てみると、家で手伝いをしている人は上手に出来ているようです。家で食事が出来てから「ごはんよ!」と呼ばれていくのではなく、台ふきをしたり、お皿やコップを並べたり自分に出来ることはお手伝いしてみましょう。きっと、給食準備も早くできるようになり、給食の準備が楽しくなりますよ。
・麦ご飯
・白菜の味噌汁
・千切り大根の炒め煮
・牛乳

・麦ご飯
・白菜の味噌汁
・千切り大根の炒め煮
・牛乳

2月5日 月曜日
今日はすきやきうどんです。みなさんの家では鍋を食べたあと、ごはんや麺を入れたりしませんか?鍋のあとは、肉や野菜などいろいろな旨みがたくさん出ているので、その中にごはんや麺を入れて食べるととてもおいしいですね。今日はすきやきにうどんを入れてすきやきうどんにしてみました。
・減量しそご飯
・すき焼きうどん
・レンコンサラダ
・牛乳

・減量しそご飯
・すき焼きうどん
・レンコンサラダ
・牛乳

2月2日 金曜日
2月3日は「節分」です。昔の節分は、春夏秋冬、それぞれの季節の変わり目をさしました。なぜ今は春の節分だけ残ったかというと、2月4日の「立春」が一年の始まり元旦にあたり、その前日の「節分」は大晦日にあたる、とても大切な日とされていたからです。節分といえば豆まきが代表的ですね。「鬼は外~!!」の掛け声で悪いものを家の外に追い払います。そして、豆を年の数ほど食べると、一年を健康に過ごせると言われています。また、節分には『恵方巻き』といって巻きずしを切らずに無言でかぶりついて食べる習慣も見られます。『恵方巻き』の恵方とは、その年の良い方角のことです。包丁で切らずに食べるのは、まわりの人との縁が切れないようにという願いが込められています。今日は手巻き寿司です。恵方巻きのようにかぶりついて食べましょう。今年の恵方は『南南東』です。
・手巻き寿司
・シイラと大豆の甘酢あんかけ
・すまし汁
・牛乳

・手巻き寿司
・シイラと大豆の甘酢あんかけ
・すまし汁
・牛乳

2月1日 木曜日
今日は高野豆腐のお話です。高野豆腐は別名“凍り豆腐”と言います。この高野豆腐は、豆腐を凍らせ乾燥させたもので、長く保存できます。実は、冬の寒い時期に、豆腐を外に放置していたことから、つくり方が偶然に発見されたものだと言われます。乾燥した状態では、スポンジのように穴があいています。この穴は作る時に、豆腐の水分が、氷になりできるものです。料理をする時は、この穴にだし汁や調味料がしみこんで、食べる時にとてもおいしく食べることができます。高野豆腐は、豆腐から作られ、その材料は大豆です。ということは、高野豆腐は体をつくる食べ物である赤の仲間です。残さず食べましょう。
・麦ご飯
・高野豆腐の卵とじ
・ワカメとツナの和え物
・牛乳

・麦ご飯
・高野豆腐の卵とじ
・ワカメとツナの和え物
・牛乳

訪問者カウンタ
1
3
0
9
9
0
0
学校行事
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
五ヶ瀬町立坂本小学校
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所3446番地
北緯32度65分、東経131度22分、標高580m
電話番号
0982-82-0588
FAX
0982-82-0589
本Webページの著作権は、五ヶ瀬町立坂本小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。
携帯電話からのアクセス
携帯電話からアクセスするには、学校ホームページのアドレスを携帯電話に直接入力する方法と下のQRコードを利用する方法があります。パソコン版も携帯電話版も、アドレスは同じです。
ただし、パケット通信料 が発生しますのでご注意ください。
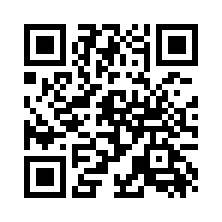
QRコード(上記画像)をバーコードモードで撮影し、取得したデータを
Bookmarkに保存し、アクセスしてください。


