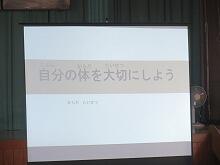学校や子どもたちの様子
 運動会で世界一の笑顔
運動会で世界一の笑顔
「どんな時でも あきらめず 世界一の笑顔で もり上がれ」のスローガンのもと、1日延期になりましたが、無事15日(月)に運動会を開催することができました。おかげさまで、当日は秋晴れで、まさに「運動会日和」でした。








徒走、リレーは手に汗握る白熱した競走が展開されました。団技では、それぞれの団が声をかけ合いながら、すばらしいチームワークを発揮しました。赤・白の真剣勝負も見所たっぷりでしたが、表現も見応えがありました。1・2年生は、「学校天国~イロトリドリノマスカットをめしあがれ~」をかわいらしく踊りました。3・4年生は、「ダイナミック川島っ子」でダイナミックな振り付けを披露しました。5・6年生は、「川島ソーラン2023」で地区の方からお借りした大漁旗をなびかせながら、本格派のソーラン節を踊りました。
各団の応援にも力が入り、リーダーを中心に活気のある声を響かせ、動きもそろっていてすばらしいの一言でした。リーダーのポンポンがまるで流れる川のように躍動しているではありませんか。競技中の応援態度もしっかりとできていました。
今年度は、なんといっても延岡名物の「ばんばおどり」が復活したというのが、地域の方々、保護者の方々にとってはうれしかったのではないでしょうか。放送で参加を呼びかける前から、来賓席近くで待機している方がいらっしゃいました。保護者の方々もすぐに踊りの輪の中に加わっていただきました。
今年度の運動会も川島小学校のみんなにとって、とっても思い出に残る行事になったことと思います。地域の皆様、保護者の皆様、熱心に応援していただき、本当にありがとうございました。
 運動会直前練習
運動会直前練習
本当は、10月14日(土)が運動会の本番でした。残念ながら、雨のため延期となり、4校時の午前中授業となりました。がっかりして学習しているかと思いきや、直前練習でもり上がっている川島小のお友達です。この切りかえの速さが、川島っ子のいいところです。





4校時にちょっとのぞいてみると、体育館で1年生はダンスの練習です。赤団の3~6年生は家庭科室で、白団の3~6年生は音楽室でそれぞれ応援練習に励んでいます。
あれ?2年生がいないぞ~と探し回っていると、いましたいました、教室で広がってダンスの練習をしていました。
明日に延期された運動会ですが、きっとみんなの輝く世界一の笑顔が見られますよ。保護者の皆様、地域の皆様の応援をよろしくお願いします。
 予行練習で確かめて
予行練習で確かめて
運動会の予行練習はしないという学校もありますが、川島小学校では、予行練習をしています。目的は2つで、係の児童の動きを確かめることと、士気を高めることです。特に前者が重要なので、以前のように全部のプログラムをせずに、内容を絞って行います。






練習とは分かっていても、全力を出して競技や演技、応援に取り組むのが川島っ子のよさでもあります。非常に力の入った予行練習でした。
今年度から、「ばんばおどり」が復活します。保護者や地域の方々にもぜひ参加していただきたいです。また、2年担任の岩切先生の指導の下、ばんば太鼓にも挑戦します。挑戦するお友達は、宇戸田 陽さん、松本 悠音さん(6年生)、高橋 佑海さん(5年生)、戸髙 直太郎さん、谷 那由他さん、寺門 昌輝さん、長野 凛さん(3年生)の7人です。本番まで1週間しかありませんが、集中して練習しています。
 階段ゴシゴシ5年生
階段ゴシゴシ5年生
10月5日(木)の朝に、5年生が階段に座り込んで黙々と何かをしています。9月に決まった、「川島小学校をもっとよくするための取組」の「朝の清掃活動」をしていました。



5年生だけでなく、運営委員会も入って熱心に清掃活動をしています。5年生が選んだ清掃場所は、中央階段です。ここにみんなで広がって、しつこい黒ずみをぞうきんでゴシゴシこすり取ります。なかなか落ちない黒ずみですが、磨いただけきれいになっていきます。
こうして、熱心に清掃活動をすることで、校舎がきれいになるのはもちろん、みんなの心もきれいになり、「利他」の気持ちも育つのです。
 運動会の練習がんばるぞ!!
運動会の練習がんばるぞ!!
10月最初の月曜日(2日)全校のみんなで運動会の練習に取り組みました。今日からぐっと秋らしい天候になり、かなり涼しくなっていますので、運動会の練習にはもってこいです。全体での練習は、本日が2回目になります。1回目は、雨のため、体育館で開会式や閉会式の練習をしましたので、今回の練習で初めて運動場で練習しました。




開会式の入場からエール交換までの流れを練習しました。各団のリーダーが積極的に声をかけながら整列したり、位置を確かめたりします。とっても頼もしいリーダーです。エール交換では、団長が運動場いっぱいに響き渡る声で、みんなを引っ張っています。
運動会では、団長や副団長がリーダーと協力しながら、自分の団を盛り上げ、心に残る運動会にしていくことでしょう。
 ほうれん草の和え物、ゆでたジャガイモ最高!~5年生の調理実習~
ほうれん草の和え物、ゆでたジャガイモ最高!~5年生の調理実習~
5年生は、「ゆでたらどうなるのかな。」というめあてで、調理実習をしました。ゆでる野菜は、青菜の代表ともいえるほうれん草、そして秋においしいジャガイモでした。担任の飯村先生と栄養教諭の土井先生、3組担任の米良先生が指導に当たります。




最初に栄養教諭の土井先生から、ほうれん草やジャガイモを調理するときに気をつけることについてお話がありました。おいしくゆでるためのポイントは、ゆで加減です。ゆですぎてもゆで方が足りなくてもいけません。ほうれん草は、軽くゆでて水にとるタイミングが大切です。ジャガイモは、竹串で刺して、ゆで具合を確かめます。また、ジャガイモの芽には「ソラニン」という毒が含まれているため、皮むきのときにていねいに芽を取り除いていきました。
おいしいほうれん草の和え物とゆでたジャガイモをみんなで試食しました。お家でもゆで野菜に挑戦して、家族と一緒に食べたり、お弁当などに入れたりしてみましょう。
 応援を盛り上げるために~応援伝達~
応援を盛り上げるために~応援伝達~
運動会まであと2週間ほどになりました。この時期、応援練習はかなり加熱します。リーダーを中心に応援練習を進めていきますが、動きをそろえるためには、全体への応援伝達の時間が必要になります。




赤団、白団が運動場と体育館に分かれて、それぞれ工夫した応援を伝達していきます。驚きなのは、毎年応援のメニューが変わっています。昨年度までと同じような応援もありますが、その年の流行を取り入れたり、話題になった言葉を取り入れたりしながら、絶えずアップデートしています。だから、とっても見ていて楽しくなります。
リーダーの皆さんは、きっとこの応援の内容を考えたり、動きを工夫したりしてアップデートさせていくところにやりがいを感じているのではないでしょうか。
 姿勢は正しくできていたかな?~9月の全校朝会~
姿勢は正しくできていたかな?~9月の全校朝会~
9月の最後の金曜日(29日)に全校朝会で9月の生活目標「正しい姿勢で授業をうけよう」の振り返りを行いました。教務主任の佐藤先生が担任の先生方に聞いたところによると、17名のお友達が特に姿勢がよかったという評価でした。


9月に姿勢が正しかったと評価されたお友達は、
1年生 岩切 心音さん、矢野 心晴さん 2年生 茂 凜緒さん
3年生 大西 結菜さん、古小路 一樺さん、寺門 昌輝さん、戸髙 直太郎さん
4年生 島田 理史さん、甲斐 絢萌さん、黒木 野乃花さん、清水 美結さん、黒木 椋介さん
佐伯 優里愛さん
5年生 木原 美優さん、堀田 菜々緒さん 6年生 横田 逢和さん、島田 梨央さん
でした。このお友達を手本に、正しい姿勢が全校に広がることを期待します。
次に、養護教諭の戸髙先生より、10月の生活目標「自分の体を大切にしよう」についてのお話がありました。10月は、自分の目標を一つ決め、それを意識しながら生活するようにしていきます。目標は、「こころ」と「からだ」に関して決めていきます。「からだ」については「早寝・早起き」「時間を決めてゲームやスマホをする」「水分補給」などが考えられます。「こころ」については「家族と話す」「お風呂でゆっくりする」「外で友達と遊ぶ」などが考えられます。自分で決めた目標は、「げんきの木」に貼り付けることで、意識を高めたり、ともだちの目標を参考にしたりするようにします。10月から、少しずつ寒くなります。自分の体を大切にしなくては、いろんな病気に負けてしまいます。
 9月の学校参観日
9月の学校参観日
夏休みが終わって、2週間ほどが過ぎた9月14日(木)15日(金)に参観日を実施しました。14日(木)は4・5・6年生の参観日で、15日(金)は1・2・3年生の参観日でした。




1日目の授業参観は、4年生が国語で「いろいろな意味を持つ言葉」、5・6年生は合同の学級活動で「スマホ・携帯教室」を実施しました。スマホ・携帯教室には、人権擁護委員協議会の甲斐さん、秋吉さん、村田さん、宮崎地方法務局延岡支局の岩本さんをお招きしました。午後の授業ですが、たくさんの保護者の方に参観していただいたおかげで緊張感をもって学習することができました。
2日目の授業参観は、1・2年生は合同の学級活動で「非行防止教室」、3年生は道徳で「黄金の魚」でした。非行防止教室には、延岡警察署の石本さん、スクールサポーターの興梠さんにおいでいただきました。どの学年も真剣な表情で授業に臨むことができました。
授業参観の後は、懇談会で、夏休みの生活の反省をしたり、2学期の予定などを確かめたりしました。
 赤団・白団でいざ勝負!結団式
赤団・白団でいざ勝負!結団式
10月14日(土)に予定されている運動会の結団式を9月15日(金)の朝に行いました。ついに、赤団・白団が決定しました。


今年度の運動会のスローガンは、「どんな時でも あきらめず 世界一の笑顔で もり上がれ」です。このスローガンのもと、これからの練習を残暑に負けず、熱中症対策もしながらがんばっていきます。
結団式では、赤団団長 松田雄貴さん・副団長 内布 向日葵さん、白団団長 濱田 楓さん・副団長 田島 綾乃さんがそれぞれしっかりとしたあいさつをし、みんなのやる気を引き出していました。これからの練習はますますヒートアップしていきます。そして、運動会当日には、きっと「世界一の笑顔」が見られることでしょう。
保護者の皆様、地域の皆様どうか応援をよろしくお願いします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 31 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
宮崎県延岡市川島町2770番地イ
電話番号
0982-36-0400
FAX
0982-36-0401
本Webページの著作権は、延岡市立川島小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。