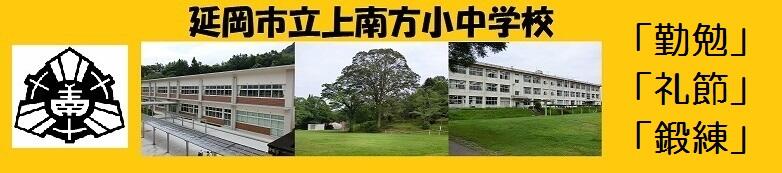
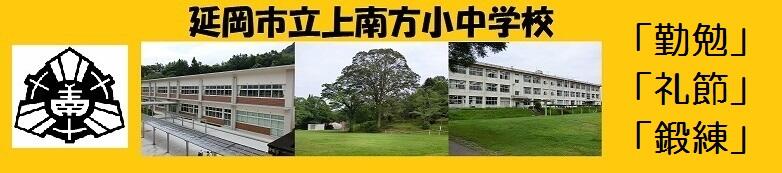
学校からのお知らせ
中学部テーマ別発表会
中学部1.2年生は2.3校時に総合的な学習の時間の成果発表の場であるテーマ別発表会を行いました。本校では、そのぞれの生徒が課題をもち、その解決方法をSDGsの関連付けながら探っていきます。2年生は課題をもって関西での修学旅行に行き、課題の解決方法や解決のヒントを持ち帰り発表会に臨みました。2年生の発表に1年生が参加することで、来年度に向けたの見通しをもつこともできました。
食育出前講座「とんとん教室」
小学部5・6年生を対象に、地産地消・食育に関する授業をJA宮崎経済連の皆様にしていただきました。今回は、「とんとん教室」ということで、最初に宮崎の養豚産業について、映像を見たりパンフレットを見ながら話を聞いたりして学びました。そして、ウインナー用に加工した豚肉を使った餃子作りに挑戦しました。餃子の作り方の説明を聞いて、グループごとに餃子を作ります。肉を餃子の皮に包む作業が楽しそうでした。焼く調理になると、香ばしい匂いがして早く食べたくなるようでした。でき上がった餃子を子どもたちは、おいしそうに食べていました。宮崎の畜産業について知るよい体験学習になりました。


がんばった竹馬大会
本校小学部の伝統的な行事「竹馬大会」を行いました。5、6年生に竹馬を支えてもらいながら時間がかかっても最後までゴールした1、2年生、一人ですいすい歩いて行く3、4年生は、たくさんの拍手をもらいました。そして、大きな歩幅で悠々と歩いて行く姿、さっそうと馬のごとく駆け抜ける姿、自分なりのペースでゴールに向かう姿など、これまで積み上げてきた竹馬の乗り方を披露した5、6年生は、さすがでした。みんなそれぞれ自分なりのめあてをもって、一生懸命に竹馬大会に取り組む姿が、とても素晴らしかったです。寒い中、応援し見守ってくださった保護者の皆様、地域の方々、ありがとうございました。





竹馬タイム
3学期のスタートと同時に小学部の竹馬タイムも始まりました。竹馬タイムは、小学部伝統の行事として長年続いている「竹馬大会」に向けて練習をする時間です。週に2回、2時間目終了後の休み時間を20分間確保して、小学部全学年で竹馬の練習をします。初めて竹馬に乗るという1年生は、6年生に支えてもらいながら一人で乗れるように練習します。2年生以上は、40m競争のうさぎさんレース出場を目指して練習に励んでいます。
給食感謝集会
1月24日から30日まで全国学校給食週間です。全国学校給食週間は、学校給食の意義や役割についてたくさんの人に知ってもらい、これからの学校給食について考えてもらうことを目的としています。本校では、給食に関わる様々な方々(調理師さん、栄養士さん、パン屋さん、牛乳屋さん、給食運搬をする方など)に日頃の感謝の気持ちをお手紙に表しました。1月20日(金)に給食感謝集会を行い、毎日の給食の献立を作ってくださる栄養士の樋口先生(南方小)に、給食の歴史や給食の人気メニューなどのお話を聞きました。全校を代表して、保健委員会の児童生徒が、感謝の気持ちを伝え、お手紙を渡しました。給食は、郷土料理や外国の料理などいろいろなメニューが豊富で栄養価の高いものになっています。子どもたちには、給食をしっかり食べて健康な身体づくりをしてほしいと思います。
第3学期 始業式と表彰式
1月10日、第3学期の始業日でした。体育館に集まり、始業式を行いました。代表児童生徒が、3学期にがんばることと題して作文発表をしました。そして、2学期中に学習面、運動面で表彰を受けた児童生徒の表彰式を行いました。BFC作品展、読書感想文、英語暗唱、JA習字、英語検定、漢字検定、数学検定で、入賞、合格した児童生徒が表彰を受けました。それぞれの頑張りをみんなで大きな拍手で称えました。子どもたちの頑張りで、ますます学校全体が意欲的になると思います。
家庭教育学級「しめ縄作り」
12月17日、家庭教育学級で「しめ縄作り」を行いました。毎年恒例の取組で、地域の小谷喜美雄さんに講師をしていただいています。正月飾りのしめ縄の由来などの話を聞いた後、親子で藁を編んで作りました。それぞれに味のあるしめ縄が完成しました。しめ縄作りを通して、日本のお正月の伝統文化に触れることができました。


持久走大会(小学部)
12月16日に、小学部の持久走大会がありました。気温が下がって寒くなり、持久走にはもってこいの日でした。子どもたちは、11月から週に2回のランランタイムや体育の授業で、決められた時間を自分のペースで走りきる練習を積んできました。1・2年生は3分間走、3・4年生は4分間走、5・6年生は6分間走です。どの学年の子どもたちも、自分のペースで一生懸命に最後まで走り抜くことができました。子どもたちが最後まで頑張る姿にとても感動しました。





バスの乗り方教室(小学3年生)
12月15日にバスの乗り方教室に小学部3年生が参加しました。本校に宮崎交通バスが来て、実際にバスを見ながらその機能の説明を聞いたり、乗り方を確かめたりしました。子どもたちは、遠足の貸切バスに乗ったことはありますが、路線バスに乗った経験はほとんどないようで、宮崎交通の方の話を一生懸命に聞いていました。そして、実際に整理券を取ってバスに乗り、消防署見学に出発しました。
鑑賞教室を行いました
12月12日に大阪府より法村友井バレエ団に来校いただき鑑賞教室を行いました。鑑賞教室が始まると児童生徒は豪華なセット、初めて見るような衣装、キャストの方々の美しい演技に驚いていました。鑑賞教室後半には「白鳥の湖」「くるみ割り人形」などの有名な演題を披露してくれました。児童生徒は演題名を聞いたことはあっても本物を見る経験はありません。本校の体育館において全校生徒で本物を見る機会に恵まれたことに対して感謝の気持ちでいっぱいにりました。
5年生 調理実習「ごはんとおみそしる」
小学部5年生が、ごはんとおみそしるの調理実習をしました。栄養教諭の樋口先生(南方小学校)の指導の下、ごはんはお鍋で炊飯です。ご飯を釜で炊いていた時代から、「はじめちょろちょろ中ぱっぱ、じゅうじゅう吹いたら火をひいて、ひと握りのワラ燃やし、赤子泣いてもふた取るな。」という呪文のような合言葉が伝わっていますが、この合言葉どおりに炊くのは、なかなかです。子どもたちは、火にかけたガラス鍋の様子をじーっと見ながら火の調節をしていました。おみそしるの具は、豆腐とねぎとわかめです。包丁で、ちょうどよい大きさに切っていました。さて、おいしいごはんとおみそしるができたでしょうか。
しろやま支援学校との交流学習
本校は、しろやま支援学校と交流学習を行っています。昨年度に引き続き、オンラインで画面を通しての交流を各学年ごとに行っています。今日は、小学部3年生が、しろやま支援学校の3年生の友達とオンライン交流を行いました。本校3年生の児童は、リコーダの演奏や「ジングルベル」の歌を披露しました。そして、手紙や折り紙で作ったものをしろやま支援学校の友達へプレゼントしました。すると、友達からも手作りのクリスマスツリーのプレゼントがあり、子どもたちは大喜びでした。楽しい交流学習でした。
小学部6年生が調理実習
小学部6年生が、調理実習をしました。南方小学校栄養教諭の樋口先生の指導の下、ジャーマンポテトと青菜のおひたし作りに挑戦です。子どもたちは、この調理実習をとても楽しみにしていたようです。始めに、樋口先生から調理のポイントの説明を聞いて、調理に取りかかりました。グループでそれぞれの役割で作業をしながら協力して進めている姿が、とてもよい雰囲気でした。しばらくすると、家庭科室からジャーマンポテトのいい匂いがしてきて行ってみると、ジャーマンポテトと青菜のおひたしが上手に盛り付けされてあり、とてもおいしそうでした。子どもたち、なかなかの腕前です。
みやざき小中学校学習状況調査
小学5年生は、みやざき小中学校学習状況調査を実施しました。国語と算数の学力テストです。4月に行われる全国学力・学習状況調査に向けて、5年生の学習状況を把握し、課題を見つけて学力アップを図ることがねらいの一つです。今日のテストは、最初に、国語の聞き取りテストから行いました。子どもたちは、じーっと放送を聞きながらメモを取り、聞き取りが終わると、問題用紙を開き問題に取り組んでいました。とても真剣な姿でした。


学校保健委員会を行いました
専門医による健康教育支援事業として、市内にある「いのうえ整形外科クリニック」井上英豪院長先生をお招きして学校保健委員会を行いました。内容はスポーツ障害についてで、スポーツをしている中学生の体に発生しやすいスポーツ障害の原因や対処法について分かりやすく説明していただきました。また、ロコモティブシンドロームのチェック法についても教えていただき、参加した生徒・保護者の皆さんにとって有意義な時間になりました。
日産工場のオンライン見学会
小学5年生の社会科では、自動車工業について学習します。車の製造工程などは、なかなか見学ができないので、オンライン見学会に参加しました。オンライン見学会は、日産自動車九州が行っているものです。教室の大型画面を通して最新の車の製造工程の動画を見たり、説明を聞いたり、クイズで考えたりしながら楽しく学ぶことができました。また、人と環境に優しい車づくりの工夫なども学習することができました。
バレエのワークショップ
文化芸術による子供の育成事業として、バレエの公演を12月12日に鑑賞する予定です。
その公演を前に、バレエのワークショップが小学部3~6年生児童を対象に行われました。
ワークショップでは、バレエ団の紹介やバレエについての話を聞いたり、簡単なレッスンを
体験したりしました。さらに、公演当日の演目に合わせて、一部場面のレッスンを行いました。
当日の公演で、6年生児童を中心に参加する予定です。さあ、どんな公演になるか楽しみです。

音楽祭に向けて猛練習中
11月18日(金)の市小中音楽祭に、小学部は3年生と4年生が出場します。延岡総合文化センターの大舞台で、合唱曲「2分の1の成人式」と合奏曲「紅蓮華」を披露します。音楽祭が間近に迫っている今、猛練習中です。朝も、昼休みも、授業でも3・4年生が奏でる楽器の音、メロディーが響いています。本番まで、あと少しになってきました。がんばれ、3・4年生!
非行防止教室
10月27日、小学部3、4,5,6年生を対象に非行防止教室を実施しました。
警察署の方々を講師にお願いして、インターネットの使用による様々なトラブルについて学習をしました。ゲーム等での課金、ネット依存症、個人情報の流失、ネットの書き込みによるトラブルやネットいじめなど、身近に起こっているトラブルについて考え、インターネットの危険性について学習しました。
インターネットの危険性を意識し、ルールを守って安全にインターネットを使ってほしいと思います。
楽しかった宿泊学習~思い出をたくさん作ってきました~
10月20日(木曜日)から21日(金曜日)にかけて、5年生が1泊2日の行縢宿泊学習に行ってきました。
大変な山道も友達と協力して乗り越えました。
帰ってきて友達と部屋で過ごした楽しい時間。
おなかペコペコで食べるおいしい夕食。
天体ドーム・天体望遠鏡を使った天体観測。
2日目には、杉焼板細工を工作したり、お世話になったむかばき青少年自然の家の掃除をし たり、とても楽しい2日間を過ごしました。
この2日間で、子供達も一回り大きく成長することができました。







| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 2 | 28 | 29 1 | 30 | 31 1 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 1 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 |
16 | 17 1 | 18 2 | 19 1 | 20 1 | 21 2 | 22 |
23 | 24 | 25 1 | 26 | 27 1 | 28 1 | 29 |
30 | 1 4 | 2 | 3 | 4 1 | 5 1 | 6 1 |
パブリック
〒882-0074
宮崎県延岡市細見町2971番地13
電話番号0982-39-0804
F A X0982-41-0153
本Webページの著作権は、延岡市上南方小中学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。





























































