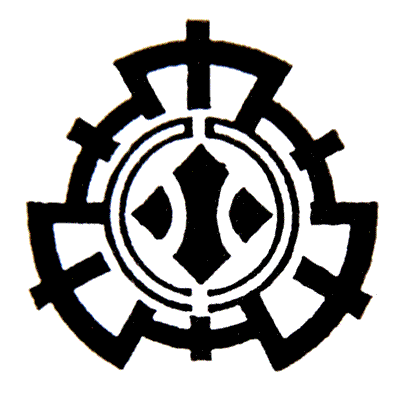学校行事
第2回奉仕作業
9月3日(日)に第2回奉仕作業を行いました。多数の保護者、4~6年児童、職員で校内の環境整備を行いました。運動場の草取り、花壇の整備、樹木の剪定などを行いました。2時間ほどの作業でしたが、校内がとてもきれいになりました。9月16日(土)の小中合同運動会は、すばらしい環境のもとで実施できそうです。




めしげ踊り
9月1日(金)の6校時の総合的な学習の時間に、5・6年生が地域の伝統芸能である「めしげ踊り」についての学習をしました。3名の保存会の方から踊りの由来、歌詞の意味、衣装の意味、振り付けの意味などを分かりやすく教えていただきました。子どもたちは、「めしげ踊り」についての理解が深まり、運動会に向けての踊りの練習にも力が入っています。
第1回小中合同練習
8月30日(水)に第1回小中合同練習を行いました。始めに、小学校、中学校の実行委員長があいさつをしました。その後、入場行進・開会式・閉会式の練習をしました。中学校・小学校の各団長、副団長、リーダーを中心に、素早く整列をし、元気よく行進をしていました。暑い中でしたが、開閉会式の練習にも集中して取り組むことができました。

全校体育
残暑厳しい晴天の下、第1回の全校体育を行いました。入場行進や開閉会式の練習を行いました。途中、こまめに水分補給の時間を取りながら、練習を進めていきました。団長・リーダーを中心に、全員一生懸命に取り組んでいました。




通学路安全点検
8月28日(月)に「通学路安全推進会議」を行いました。これは、「小林市交通安全プログラム」に基づき、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保のために実施するものです。学校、PTA、区長、市会議員、土木事務所、警察署、市建設課、市危機管理課、市学校教育課、スクールガードリーダーなどが参加しました。始めに、校区内の危険箇所への対応についてこれまでの取組の概要を確認しました。その後、改善が必要な箇所の現地へ行き、子どもたちが安全に通学できるよう今後の対策を確認しました。








1学期後半スタート
8月25日(金)から1学期後半が始まりました。楽しい夏休みも終わり、子どもたちは、元気に登校してきました。業間の時間には、「夏休み明け全校集会」を行いました。教頭の話の後、9月の生活目標について、体育主任が話をしました。9月の生活目標は『運動会を成功させよう!』です。「あきらめず」「協力して」取り組むことを話しました。暑い時期ですが、初日から運動会の練習に取り組んでいきます。子どもたちの体調に配慮しながら運動会に向けての練習に取り組んでいきたいと思います。 
永久津校区夏祭り
8月13日(日)に永久津校区夏祭りがありました。この夏祭りは、実行組織「永久津ドンとやろう会」が中心になって企画運営し、地域全体で一体となって永久津の素晴らしさを再確認できるような夏祭りを目指して実施されているようです。当日は、たくさんの人が会場に来ておられました。また、小学生が絵を描いた灯籠もたくさん飾ってありました。
そうめん流し、綱引き、ダンスや太鼓の演奏などで会場は大変盛り上がりました。小学生は、「校歌」と「ありがとうの歌」を歌いました。元気の良い歌声に、会場から大きな拍手をいただきました。
後半は、大抽選会や大花火があり、祭りの最後を盛り上げていました。

そうめん流し、綱引き、ダンスや太鼓の演奏などで会場は大変盛り上がりました。小学生は、「校歌」と「ありがとうの歌」を歌いました。元気の良い歌声に、会場から大きな拍手をいただきました。
後半は、大抽選会や大花火があり、祭りの最後を盛り上げていました。

平和学習
8月2日の登校日に平和学習を行いました。まず、教頭が戦争や平和についての話をしました。その後、学級ごとに体育館後方に展示した戦没者の遺品を閲覧しました。この遺品は、平和学習のために宮崎県遺族連合会よりお借りしたものです。「戦時中の写真」「防空頭巾」「召集令状」「死亡通知の電報」「家族への手紙」など多数の展示物を、担任が解説しながら閲覧していきました。低学年の児童も、担任にたくさん質問をしながら見ていきました。児童は、平和への思いをさらに強く感じたようでした。








PTA家庭教育学級
7月26日に家庭教育学級を行いました。NTTdocomoの方を講師に招いて、「スマホ・ケータイ安全教室」を行いました。「最近の子どもたちのケータイ事情」「子どもにインターネットを使わせる際の注意点」などを話していただいた後、子どもたちが巻き込まれた実際のトラブル事例を紹介していただきました。『子どもを守るために親として何をすればよいか』がわかり、大変有意義な研修会となりました。




木工教室
放課後子ども教室主催の木工教室を行いました。多数の親子が参加しました。始めに、西諸地区森林組合の方が、山や木に関する話をしてくださいました。その後、親子で、椅子や飾り棚を作っていきました。慣れない手つきの子供たちをお父さん、お母さんがサポートしながら、全員が作品を完成させました。